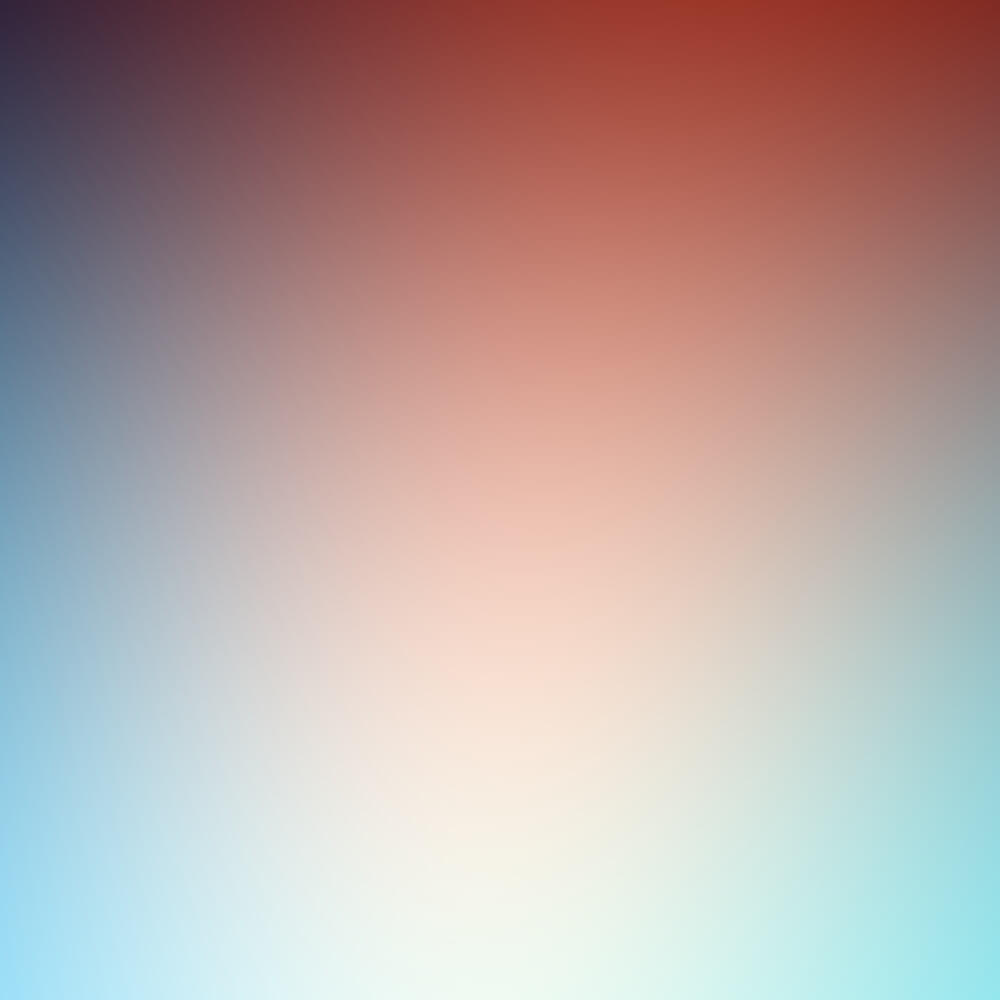👨👩👦👦
父のジレンマ
きっかけ
誰だって、名刺に書いてある役職名は、何歳になっても変えることができる。でも頭の中、というか「考え方」は、20代の終わりくらいまでに形成されるものだと思う。
僕は故郷の青森から、よくあるルートを通って少し都会の仙台に出て、またまたよくあるルートを通ってトウキョウの総合商社へ就職した。 まぁ自分で言うのも変な話だが、僕の両親世代が安心するコースだったと思う。しかしそれは24年目の春に途絶え、NPOで1.5年、そして今ではスタートアップで創業メンバーとして1.5年ほどやっている。「将来は安泰だ」という両親の期待は見事に裏切られた。それで良いのだ。安泰な将来などこの世は無いのだから。
僕の名刺
コースを脱線した後の職務人生はとても充実していた。
お金集め、事業の立ち上げ、マーケティングやら、オペレーションの構築、商材の仕入、プロダクトマネジメントと常に役割を転々とし、その都度「ディレクター」「マーケター」「Product Manager」などのわかりやすい肩書を自分に与えて他者に説明する必要があった。 けれども、こんな転々とする肩書とは違って、僕にとっても岩田社長のソレと同じように、心に決めた永遠に変わらない肩書があった。
それは「父」であり「アスリート」であることだ。 そしてこの2つの肩書は、本当によく喧嘩する。
この記事は自分の中の葛藤にをさらけ出しただけのポエムで、誰の役にも立たないかもしれない。 けれども、僕と同じように心の肩書が喧嘩してしまう人に少しは役に立つかもしれない。
父であるとは
イクメンという言葉が世の中の通念となって久しいが僕はこの言葉がとても嫌いだ。 仮に子育てに精力を出す男性をイクメンと呼ぶのであれば、その替わりに僕は父と呼ばれたい。
父であるとはどんなことなんだろうか。 父には、父であるための、沢山の仕事がある。
- 母親のサポートをすること。父の育児は母親の穴を埋めることから始まる。
- オシメをかえること。パンパースの真ん中にあおい筋が入ったらチャンス。
- 知的創造力を養う機会を創ること。滑り台100往復もそのためさ。
- 一緒にごはんを食べること。一人じゃみかんの皮、むけないからさ。
- 寝かしつけをすること(たまに一緒に寝てしまうこと)。寝ている息子は親指をよく吸っていて、寝顔は破壊的である。
- 朝起こされたら、どんなに眠くても、一緒に起きて一日を一緒に始めること。おはよう。
- オシメを替えること。何度でも。
- 一緒に笑うこと。あはは。
- ものを投げたら、叱ること。こら、危ないでしょ。
- 絵本を読んであげること。「犬」→「わんわん!」「豚」→「ぶーぶー」「お父さん」→「…」え。。。
- ほめてあげること。よく歩いたね。
- 外から帰ったら、一緒にうがいをすること。吐き出さず90%は飲んじゃうけどね。
- お風呂に一緒に入ること。溺れたら困るしね。
- 歯ブラシをしてあげること。赤ちゃんは自分で磨けない。
- 保育園への送り(と、たまにお迎え)をすること。朝の自転車で、すれ違うトラックを指差して「トラック」と言い合う時間は、至福の時だ。
- 泣いた時に見守って泣き止むためのサポートをしてやること。絵本を読むことが多いね。
全て読んだ人はいないだろう。大丈夫。沢山あるんだね、というところだけ抑えてもらえれば。
父に必要な時間
父の在り方は本人の心の持ちようや心の肩書に寄って千差万別だ。毎日の「父」の仕事は絶えず変わり続ける。 ひょっとしたらゼロの日もあるかもしれないが、妻と助けあって僕は僕を父にしている。
(そうか、彼女がいなければ僕は父になることができないのかもしれない。)
兎にも角にも、父であることは父であるための仕事をすることでなんとか保たれている。 父には父のための仕事があり、そのための時間が必要だ。
上記のリストに書いた一つ一つの項目は、あえてすべてA+Bという2つの文で作っている。 それはAという仕事にはかならずBという思想だったり、感嘆だったりが付随することを伝えたかったからだ。
これは何を意味するか。
父にはAをこなすだけの時間が必要なのではない。AとBのための時間が必要なのだ。 分単位で切り詰めたような時間ではなく、子がもたらす不測のカオスを受け止めるだけの余裕を含めた、真の意味での「時間」が必要だ。
ドイツの詩人、ウィルヘルム・ブッシュはこう言った。
父親になるのは簡単だが、父親たることはなかなか難しい。
父親であること。 それは父親であろうとする時間と向き合うことなのだと思う。
アスリートであるということ
対して、アスリートであるとはどういうことか。
僕にとって「アスリート」という存在は特別なものだ。 人には誰にだって無意識にディグり((dig = 掘るから来ている))たくなるほど好きなモノがある。僕はバスケが狂うほど好きだった。でも飽き性だったから、次にラグビーが好きになった。でも飽き性だったから、今度はアメフトが好きになった。
そして最後に好きになったのは、スポーツで勝つことに向き合う人のもつ精神だった。これは今もずっと好きだ。
だから僕にとってのアスリートという言葉は、オリンピックに出るとか、日本代表になるなどの「競技的に有能な成功者」を指すものでない。 自分が登ろうと決めた山への向き合い方、プロフェッショナルな精神を「アスリート」と呼んでいる。アスリートは現代の求道者だ。
余談ではあるが、僕は物心ついてから22歳くらいまで、殆どの期間をスポーツで成果を出すために使ってきた。しかし能力とかセンスとかいろいろ足りなさすぎて輝かしい成績を修めたことはない。でも未だにそれを諦められないでいる。スポーツのトップクラスというのは同世代プラスマイナス10年程度の帯での勝負だと思うが、僕はマスターと呼ばれる60代以降の競技で何らかの世界一を取ろうと本気で思っている。いまは勝てない人が老け込んだ時に襲おうというゲスい考えを未だに持ち続けている。
アスリートにも時間が必要
アスリートは忙しい。例えば、
- 自らのパフォーマンスを最大化するための体作りを行うこと。
- 1g単位で、自分が摂取する栄養素と向き合うこと。量や質だけでなく、タイミングも重要だ。
- イメージを作ること。[asin:4877713166:title]にあるように、身体を動かす、というパフォーマンスも、知的創造をする、というパフォーマンスもそのリミットは自身の思考によって決められる。((ちなみに競技アスリートであれば「どんな動きを行いたいのか」というイメージを作るために、膨大な量のフィルムスタディを行う。僕もアメフトを行っていた時、生活の1/4はひたすらビデオを見ることだった。))
- 戦略と、戦術を練ること。特に相手がいる球技などのスポーツでは、相手をどう攻略するか、という点で高度な思考が必要になる。
- 戦術を遂行するために、イメージ通りに身体が動くまで、ひたすら反復を繰り返す。練習とはこのレベルで追求しないと意味が無い。
- 体調を整え続けること。「1日休むと取り戻すのに3日かかる」と語った柔道・やわらちゃんの言葉を僕は忘れない。
それは突き詰める作業の連続である。 ウサイン・ボルトは生まれながらに100mを9秒台で走ったわけではなく、猛烈な時間を投資して結果を作っていった。マイケル・ジョーダンも、トム・ブレイディも、皆そうだ。
余談だが、この精神を体現する僕の大好きなキャラクターがいる。 「HUNTER×HUNTER」という漫画にでてくる、キルアという殺し屋だ。 彼は主人公のパートナーとして、アスリートな一面を見せて僕を魅了してくれるのだが、なかでも好きな一言がある。
毎日完璧な体調管理をこなしながら致死量ギリギリの毒を何時(いつ)でも躊躇いなく飲める奴が生き残れるんだ
https://amzn.to/2Vg0o2P
殺しのプロとして、いついかなる時でも自身の最大のパフォーマンスをできるよう、準備を怠らない。この精神こそアスリートがもつ非凡な魅力だと思っている。アスリートは、プロフェッショナルという言葉と置き換えられるかもしれない。 初見から10年以上たったと思うが未だに大好きなセリフだ。
父のジレンマ
僕が内面に飼っている「父」と「アスリート」という肩書はよく喧嘩をする。
スタートアップで働くということはある種知的アスリートであることを義務付けられる。日々自分をupdateするための時間が必要で、それは「父」でありたい僕と喧嘩をする。 どちらかに割りきってどちらかを捨てるような選択ができればこの悩みは解決するのだが、「父で(知的)アスリート」でいたい僕はいつも決断を迫られる。
今日は父をするか、アスリートをするか。いつも悩んでいる。父のジレンマ だ。
タイミングによって、どちらを選ぶのかの決断が簡単な時もあれば難しい時もある。
仕事が山の時は、家族に断って「アスリート」を選べばいい。そうじゃなければ「父」を選べばいい。けれども、そんなわかりやすいシチュエーションはなかなかないもんだ。
そんな迷いに対して答えを出したい時、拠り所になる考え方がある。
ゴーイング・コンサーン
はてブ界隈で有名なベンチャーで働くユウタロス(@grand_bishop)さんという人がいる。 最期に見る夢をいくらで買いますか?というFBで6,000以上もシェアされた記事の一節から、僕は父のジレンマを改めて考えさせられる。
ゴーイングコンサーン(継続企業の前提)という言葉をご存じだろうか。企業が将来にわたって無期限に事業を継続することを前提とする考え方のことで、企業は始めるにも経営するにも、この考え方を礎としている(中略) しかし、人は逆だ。必ず死ぬ。誰しも知っている事実だが、なら、死ぬことを前提に生きるとき、時に「死なないことを前提にした企業や資本主義の枠組みの中での合理性」が期限付きの人間には必ずしも合理的でない
一方で「期限付き」の人間は、子供を産み育てていく。
父になるということは、永遠につづくはずのない「人間」「自分」という存在を子に投影することを許されることでもある。 本来、数十年という時間で途絶えていく自分という存在を、子が繋ぎ、ゴーイング・コンサーンな存在として未来をメタ的に生きていくことができる。
そう理解した瞬間、「父のジレンマ」に迷った時、どんな答えを出せばよいかシンプルに考えられる様になった。
父が子に対し注ぐことのできる時間は、せいぜいたったの20年弱だ。成人すると、子は親元を離れ、自分の生活を創っていく。子はまた子を育み、そうやって血が紡がれていく。その年月は、個体としての僕の寿命を何倍、何十倍と越えていく。
父となる時間は、運命のいたずらか、もっとも生物として脂が乗った時にくる。女性にとっても同じかもしれない。僕にとってもそうだ。「父のジレンマ」は起きるべくして起きている。
けれども、迷った時の答えの出し方は、「自分をゴーイング・コンサーンな存在」として再定義できれば、きっとすんなり分かるんじゃないだろうか。

すべての「父のジレンマ」に悩む人へ。子供は僕やあなたを未来へ連れて行ってくれる。子どもと向き合う時間は、長い目線で見れば、僕やあなたのする仕事を凌駕する価値を持っている。仕事は本来楽しいものだ。趣味もあるだろう。でも僕やあなたにはもっと価値のある人がそばにいることを忘れずに、ジレンマに向き合っていこうじゃないか。